はじめに
イギリスのシンクタンクCEBRの予測によると、日本のGDPは2039年に世界5位に後退するとされています。この記事では、その背景にある経済状況、各国のGDPランキングの変動、そして今後の経済動向について専門的な視点から分析します。
1. 日本のGDP世界5位に後退へ、米中はトップ2堅持-英シンクタンクの予測
イギリスのシンクタンクであるCEBR(経済ビジネス研究所)が発表した予測によると、2024年時点での日本のGDPは、アメリカ、中国、ドイツに次いで世界4位に位置づけられています。この予測は、日本経済が直面している課題と、世界経済における日本の立ち位置の変化を浮き彫りにしています。
内閣府が公表する2024年7~9月期の実質GDP成長率(1次速報値)は、前期比+0.1%(前期比年率換算+0.4%)と予測されています。この数値は、景気が緩やかな持ち直しを続けているものの、そのプラス幅は小さく、持続性に乏しい状況を示唆しています。
特に注目すべきは、設備投資の動向です。設備投資は前期比で微減(0.1%)と予想されており、2四半期ぶりの減少が見込まれています。これは、企業が将来の経済状況に対して慎重な姿勢を崩していないことを示唆しています。
さらに、個人消費も依然として力強さに欠けています。個人消費は前期比で小幅な伸び(0.3%)にとどまるとみられており、経済成長を牽引するほどの勢いは見られません。物価上昇や賃金の上昇が消費者の購買意欲に十分につながっていない現状がうかがえます。
一方で、輸出は前期比で+2.3%と2四半期連続の増加を予想されています。これは、中国向けの輸出が停滞しているものの、EU向けやNIEs(新興工業経済地域)向けの輸出が持ち直しているためです。しかし、輸出の回復が日本経済全体を力強く押し上げるには、他の経済指標の改善も必要不可欠です。
これらのデータから、日本のGDPは2024年7~9月期にプラス成長を維持するものの、その成長率はごくわずかであり、経済の足取りは依然として重いと言えるでしょう。個人消費や設備投資の弱さが懸念される一方で、輸出の持ち直しが見られるものの、その持続性には不透明感が残ります。
2. 日本のGDPの予測とその背景
日本の国内総生産(GDP)が2039年に世界5位に後退する予測が、英シンクタンクの経済ビジネス・リサーチ・センター(CEBR)によって発表されています。以下にその詳細をまとめます。
日本のGDPの現状と予測
- 現在の順位: 日本のGDPは2024年の時点では、米国と中国に次ぐ世界第4位です。
- 予測: 2039年には、インドが3位に躍進し、ドイツが4位になるため、日本のGDPは5位に後退する予測されています。
米中の経済力
- 米国の経済力: 米国は現在世界最大の経済大国であり、短期的にはその地位を維持する予定です。
- 中国の経済力: 中国は近年急速に経済発展を進め、短期的には米国の経済大国としての地位を狙っています。ただし、構造的および人口動態的制約が存在するため、その期間は短くなる可能性があります。
欧州諸国の経済力
- ドイツの経済力: ドイツは現在英国を上回るGDPを持っていますが、経済パフォーマンスで後れを取っているため、15年後にはその差が20%に縮小する可能性があります。
- 英国とフランスの経済力: 英国とフランスは現在もGDPの順位を維持しており、39年後にはそれぞれのGDP規模が大きくなる予測されています。英国はフランスをしのぎ、GDP規模が25%大きくなる可能性があります。
これらの予測は、各国が経済成長や人口動態などの要因に基づいて行われています。
3. 欧州諸国の経済動向
欧州諸国の経済動向について説明します。ドイツが順位を下げ、イタリアが上位10カ国から脱落する一方、英国とフランスは6位と7位を保つ見通しについても触れます。
欧州諸国の経済動向
ドイツの経済状況
ドイツ経済は、ユーロ圏経済の成長が鈍化する中で、製造業の不振が続いています。構造問題や中国の内需低迷、コスト高などが生産活動を阻害しており、2024年のGDP成長率は+0.2%、2025年は+1.0%と予測されています。名目GDPは成長しているものの、実質GDPはマイナス成長となっており、構造的な課題が浮き彫りになっています。
イタリアの経済状況
イタリアの経済は、2024年にマイナス成長となる見込みです。供給面では農林水産と工業が減少しており、サービス業の成長で一部を補っている状況です。ユーロ圏内でも、特に経済の停滞が目立つ国の一つとなっています。
フランスとスペインの経済状況
フランスはオリンピック特需により観光と消費需要が高まり、経済活動が促進されています。2024年のGDP成長率は+0.4%と、比較的高い成長率を維持しています。一方、スペインも同様に高い成長率を示しており、前年同期比で回復が進んでいます。
英国の経済状況
英国はユーロ圏を離脱した後も、比較的安定した経済状況を維持しており、GDPランキングでは6位を保つ見通しです。
このように、欧州諸国の経済動向は、ドイツの製造業の不振やイタリアのマイナス成長など、各国特有の要因によって異なる展開を示しています。ユーロ圏経済全体としては緩やかな回復に向かっているものの、力強さに欠ける状況が続いています。
4. 中国との競争
中国との競争について説明します。中国がいずれトップの座を占めると考えられますが、構造的・人口動態的制約を前提として、世界経済のリーダーの期間は短いだろうと見解が示されています。
中国の経済成長
中国は比較的短期間で貧困を脱し、中所得国へと移行しました。過去5年間で、名目GDPの平均成長率は16.4%、実質GDPは10.4%と高成長を遂げていました。この高成長は、人口の大部分が農村部から都市部に移行し、億単位の国民が中産階級へと押し上げられることで推進されました。中国は今や世界最大の自動車市場と自動車輸出国でもあり、世界経済においてその規模を大きく増加させています。
実質GDPと名目GDPの比較
実質GDPを基準にみると、日本の経済規模は中国よりも3倍も大きいと計算されています。名目GDPでは、中国はインフレ要因が為替レートで調整されなかったため、日本経済に追いつきやすいとされています。実質GDPが国の生産力を示すものであれば、日本は同一金額のコストで中国の3倍の生産物を生み出していることになります。
中国の将来の成長
中国経済の専門家であるマイケル・ペティス氏は、今後10年間の成長にはブレーキがかかり、最善のシナリオでも年間成長率は4%を超えることはないだろうと述べています。中位のシナリオでは、成長率は年間1.5~2%となり、成熟した経済大国である米国の成長を上回ることはないとの見解があります。下位のシナリオにおいては、中国は世界最大の経済大国である米国に追いつくことはないと想定されています。
中国との競争の展望
中国がいずれトップの座を占めると考えられますが、構造的・人口動態的制約を前提として、世界経済のリーダーの期間は短いだろうと見解が示されています。例えば、イギリスのシンクタンクであるCEBRは、日本のGDPが2024年の時点では米中、ドイツに次いで世界4位であることを予測していますが、日本のGDPが2039年に世界5位に後退する可能性もあります。このため、中国がトップの座を占めるのではなく、米国が世界最大の経済大国を維持する可能性が高いと考えられています。
5. インドネシアの経済成長
インドネシアの経済成長は、安定した消費者支出、増加する投資、輸出の拡大に支えられており、2024年におけるGDP成長率は5.5%に達しています。これはアジア太平洋地域で注目される経済大国としての地位をさらに強化しています。
2023年におけるインドネシアのGDP成長率は5.05%で、前年と比較して伸びました。経済活動は新型コロナウイルス感染症の影響から徐々に回復しています。特に家計消費、政府支出、固定資本形成が増加しており、運輸・倉庫業、サービス業、宿泊施設・飲食サービス業が高い成長率を記録しています。ただし、輸出は微増に留まり、輸入はわずかに減少しています。
国際通貨基金 (IMF) は、インドネシアの経済成長が2035年には世界の8位に浮上する予測しています。IMFは、2027年までに一人当たりGDPが6,500ドルに達すると予測しており、2010年から2021年の間には平均年率4.7%で成長し、世界193か国・地域中35番目に位置する高い成長率を維持しています。
インドネシアは、経済成長とともに物価の安定も維持されています。2021年の消費者物価上昇率は1.9%、コアインフレ率は1.6%であり、これは過去10年間で最も低い水準を記録しています。
2024年はインドネシアで大統領選挙が行われる年であり、プラボウォ・スビアント国防相が多くの民間調査機関により当選確実とみなされています。この選挙では、新しいリーダーシップのもとでインドネシア経済がさらなる発展を遂げることが期待されています。
おわりに
本ブログでは、最新の経済動向と将来予測に基づき、日本のGDPの現状と課題、そして世界経済における日本の立ち位置の変化について詳しく解説しました。
まず、日本のGDPが2024年には世界4位に位置するものの、2039年には5位に後退するという予測に焦点を当てました。内閣府のデータに基づく最新のGDP成長率の分析から、個人消費や設備投資の弱さが経済成長の足かせとなっている現状を明らかにしました。一方で、輸出の持ち直しが見られるものの、それが経済全体を力強く牽引するには不十分であることも指摘しました。
次に、世界経済の動向として、米国と中国の経済力について分析しました。米国は依然として世界最大の経済大国であり、中国も急速に経済成長を遂げているものの、構造的な制約も抱えていることを解説しました。また、欧州諸国の経済動向についても触れ、ドイツの製造業の不振やイタリアのマイナス成長、フランスやスペインの好調な経済状況など、各国が抱える課題と可能性について考察しました。
さらに、中国経済の成長とその将来について、実質GDPと名目GDPの比較を通じて、中国の経済規模の実態を分析しました。専門家の見解を引用し、中国経済の今後の成長が鈍化する可能性や、世界経済におけるリーダーシップの期間が短い可能性についても言及しました。
最後に、インドネシアの経済成長に焦点を当て、安定した消費者支出や投資、輸出の拡大が経済成長を支えている状況を解説しました。IMFの予測に基づき、インドネシアが将来的に世界経済において重要な役割を果たす可能性を示唆しました。
これらの分析を通じて、日本経済が直面する課題と、世界経済における各国の動向を把握することが重要であることがご理解いただけたかと思います。今後の経済情勢を注視し、新たな情報や変化があれば、引き続きブログを通じて発信していきます。
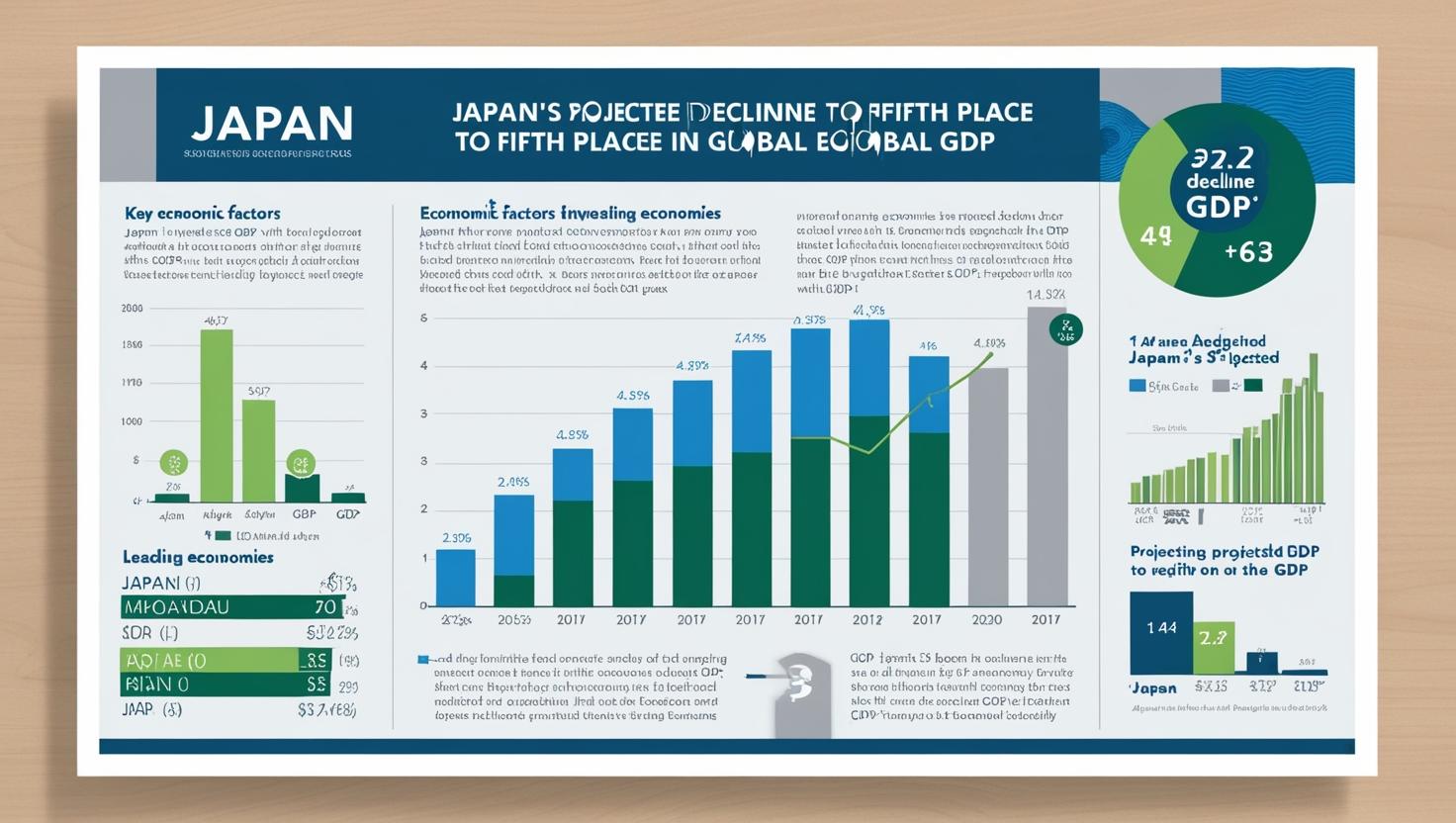
コメントを残す